端午の節句は、現在では「子どもの日」として国民の祝日の1つになっていますよね。
一般的に、「桃の節句」が女の子のお祝いであるのに対し、「端午の節句」は男の子のお祝いとして認識されています。
でも、じつはもともとは「女性のお祭り」だったっていうのはご存知でしょうか?
今回は、その由来と、そこからなぜ「男の子の節句」になったのか記事にしてみました。
端午の節句が女性のお祭りだった理由とは?
端午の節句といえば、勇ましい男の子のお祝いですよね?
でも古く遡れば、意外にも女の人の行事だった時代がありました。
むかしは、5月は田植えの月で、1年のうちでも重要な月でした。
なぜなら、田植えは、穀物の霊魂を増やすために田の神様を迎える重要な神事とされていたからなんです。
そんなことから、5月5日は「田の神様」に豊作を祈る日となっていました。
その「田の神様」を迎えるのは女性の役割で、早苗を田に植えることで迎えていました。
この、田植えをして神に奉仕する女性のことを早乙女って言います。
昔は早乙女が5月に早苗を田に植えていたんです。
そして、田植えという神事を行う早乙女は清浄さが求められていました。
この時期に自分の結婚式などの私事をおこなうことは、神をないがしろにすることとして禁じられていましたし、神様の祭りをするためには身を清め、忌みごもりをしなければなりませんでした。
これを五月忌み(さつきいみ)と言い、この日には菖蒲で亭主の尻をたたいて家から追い出し、女性だけで家にこもったので、女の家とも言われました。
また、菖蒲で家の屋根を葺く(ふく)ので、ふきごもりと言ったり、愛知県や徳島県、高知県の山中では5月4日を「女の晩」、「女の天下」と言い、昔は男性に従う一方だった女性が、この日だけは威張って良い日とされていたんです。
いつも忙しく働いていた女の人たちは、この日のおかげでゆっくり休養できたのだそうです。
「女の家」については、江戸時代の浄瑠璃作家である近松門左衛門の「女殺油地獄(おんなごろしあぶらのじごく)」という作品に「5月5日の一夜を女の家と言うぞかし」という一説があります。
大昔の日本では端午の節句は男の祭りではなく、田植えに結びついた女性の祭りだったってことが、この作品からもうかがえます。
男の子の節句になったわけは?
もともとは邪気払いと物忌みの祭りだった「端午の節句」が男の子の節句になったのは、かなり後になってからです。
貴族の時代から武士の時代になると、菖蒲打ち(しょうぶうち)、印地打ち(いんじうち)、競漕(きょうそう)、競馬(くらべうま)、流鏑馬(やぶさめ)など、勇ましい行事が「端午の節句」で行われるようになりました。
そのことと、「菖蒲」が「尚武(武を重んじること)」や「勝負」と音が同じことから、次第に男の子の節句と考えられるようになったのです。
また、家紋をつけた旗指物や「鍾馗の像」を描いた幟(のぼり)を庭に立てることも普及しました。
そして、江戸時代になると、町人のあいだで鯉が滝登りをするように勇ましくという意味で「鯉のぼり」が立てられるようになり、やがてそれが武家の間にも広まりました。
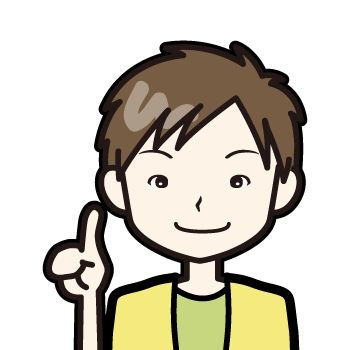
中国の魔除けの神です。唐の玄宗皇帝が病気になった際に、鍾馗が夢のなかに出てきて病気をなおしました。
それにちなんで邪気を払う神としたのが始まりとされています。
当時は、年の暮れにその像を門口に貼っていましたが、やがてそれが「端午の節句」の幟に描かれるようになりました。
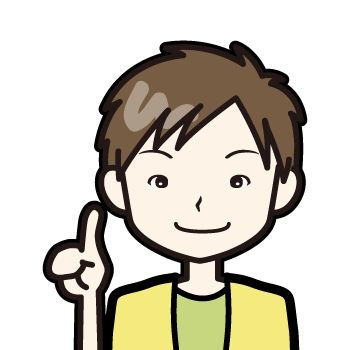
それは、古代の菖蒲鬘(あやめかずら)の代わりに菖蒲で兜を作り、その前飾りに人形をつけることが流行ったことから、武者人形が誕生したんです。
この人形には、悪霊をはらう呪物としての意味や、神送りをする際の「形代(かたしろ)」としての意味もあります。
武者人形は、初めは日本神話の神功皇后(じんぐうこうごう)と武内宿禰命(たけのうちのすくね)の姿でしたが、のちには金太郎、牛若丸、弁慶、加藤清正などが飾られるようになりました。
結局、簡単にまとめると?
田の神様をお迎えするお祭りで、若い女性が菖蒲の力で穢(けがれ)を払い清めていた。
その後、武家社会など時代に合わせて徐々に変化していった。
って、ことですね。
お役に立ちましたなら幸いです。
それでは。
こちらもいかがですか?





